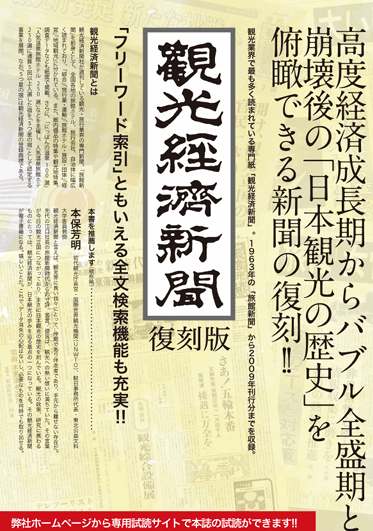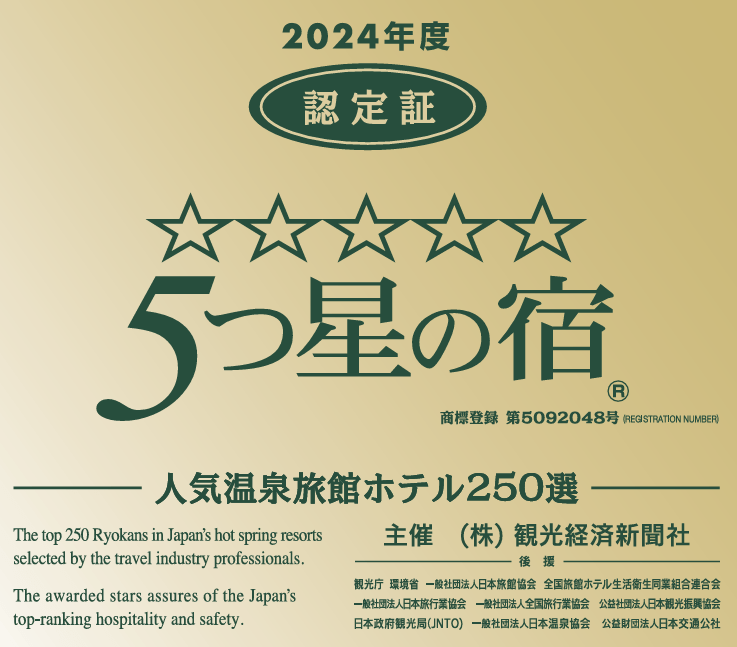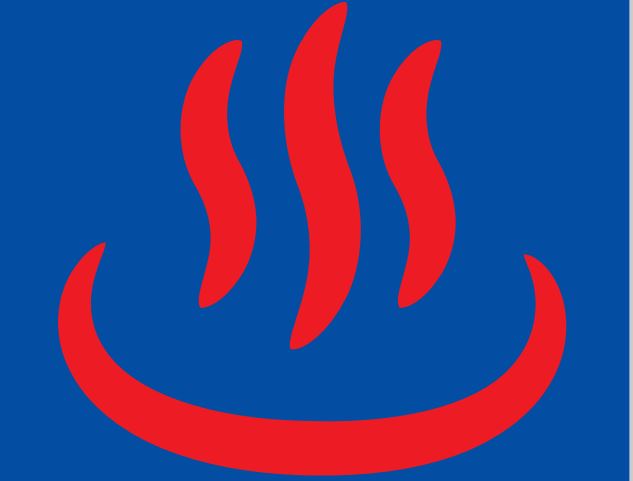1980年代半ば、「共同運行制」の定着とともに、全国の乗り合いバス事業者らは先を争うように高速バスの共同運行の「縁組」を行った。
地方部では、もともと、生活圏(各県におおむね2~3)ごとに、地元の路線バスを運行する乗り合いバス事業者が存在していた(いわゆる「戦時統合」によって、中小の事業者が合併して生まれた例が多い)。
また、大都市周辺では、京王や阪急といった大手私鉄のバス部門や子会社が路線バスを運行していた。
これらの会社は、鉄道やバスなどの運輸事業だけを行っているわけではない。百貨店やホテルの経営、都市部での不動産運営や郊外の住宅地開発、観光開発など、生活関連を中心に幅広く事業を行うとともに、それが沿線の人口増加や価値向上に貢献し、本業たる運輸業にも還元されるという「沿線経営」を行っているのだ。
阪急電鉄の創業者である小林一三が作り上げたこのモデルを真似て、全国で地域ごとに「ミニ阪急」が展開されていたのだ。
大手私鉄の場合、バスは補完的存在だが、地方部では、そのような複合企業体の基幹事業がバスである。当時は路線バスの利用者が今より多かったから(路線バスの輸送人員は1970年頃から減少を始め、現在ではピーク時の4割に過ぎない)、生活関連産業を展開する上でのブランド力の源泉は、地域内のバス路線網であった。
バス自体の存在感が低下した今でも、地方銀行や新聞社などと並んで、地元の名士企業扱いされる企業がほとんどだ。そのような会社が、自らの基幹事業の、それもフラッグシップ商品として東京や大阪行きの高速バスを運行すれば、地元での認知はおのずと高まった。
1980年代半ばと言えば、バブル期に向け経済は右肩上がりであった。また、末期を迎えた国鉄は運賃値上げを繰り返しサービスへの評判も落ちていた時期である。全国から東京や大阪といった大都市、あるいは九州一円から福岡というような最寄りの地方中核都市への足として、高速バスは地方部で一気に定着した。
(高速バスマーケティング研究所代表)